「中高年のひきこもりには二種類ある」
と筆者の桝田氏は述べています。
ここでは従来型のひきこもりについて掘り下げていきます。
従来型のひきこもりとは、
思春期から20代前半における挫折からひきこもりになり、長期化し中高年まで続いているものです。
アイデンティティとは
アイデンティティとは、アメリカの心理学者エリク・エリクソンが提唱した概念で、
二つの要素から成り立っています。

1.自己肯定感
「自分が自分でいてもいい」という感覚
自分に対して主観的に許可を出す
2.社会から認められている価値
「あなたはあなたのままでいい」という社会的に容認されている感覚
社会との相互関係の中で生まれる
この二つは連動して補完しあいます。
たとえば、望む仕事につけて、社会的に認められているという確信が高まると、多くの人は自己肯定感も高まります。
しかし解雇され、無職の状態が長引くと、社会から認められている感覚が下がり、その結果自己肯定感も下がるということが起こりやすくなります。
ひきこもりに陥る人は、もともと自己肯定感が低く、アイデンティティが脆弱な場合が多いようです。
従来型のひきこもり
本人の資質や不適切な養育経験、いじめなどが大きな原因と考えられています。

基本的信頼を得られない
その本人の資質の要因として親との関係の中での「基本的信頼」を得られていないことが多いと桝田氏は言います。
ひきこもりとは、
・自分を信じられるか
・親を信じられるか
・他人を信じられるか
という問題
そして自分を信じられないと自己肯定感にも影響していきます。
自分を信じられないことがつらい
自分で自分を信じられないことが一番つらい
自分の可能性を信じられない、自分の人生に希望を持てない、
「自分は生きていていいんだ」という希望すらも見いだせない
基本的信頼を築けないと、
「自分が自分でいてもいい」という
自己肯定感も低くなる
自己肯定感が低くなると、生きる希望を見いだせず生きていくのがつらくなります。
唯一の味方である自分を信じるということは、生きていくうえでとても重要なことだと思います。
それができないということは自分で自分のことを見張り、追い詰め、批判ばかりしていてとても苦しくなります。
ひきこもりになりやすい子どもの性格
特徴として以下のとおりです。
人付き合いが苦手、内向的、自己主張が強くない
まじめ、優しく繊細、敏感、空気を読むことに長けている
子どものころ、親の顔色をうかがってきた人が非常に多く、自分の心を押し殺して親の意向に従っている”いい子”を続けていると
「自分の欲求」ー自分が何をしたいのか
何を好きで嫌いかがわからなくなり、自己主張をできなくなる
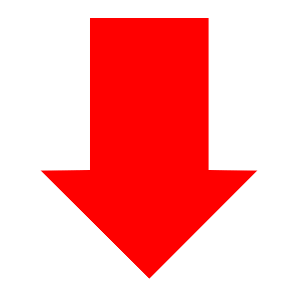

いやです!
と言えず、
相手の申し出を断ることができない
自己主張しない子、何でも我慢する子とみなされ、
いじめの標的になるケースもあります。
また大人になってからも、
職場でも面倒なことを押し付けられても文句も言わず黙々と仕事をこなす
「都合のいい人」になりがちです。
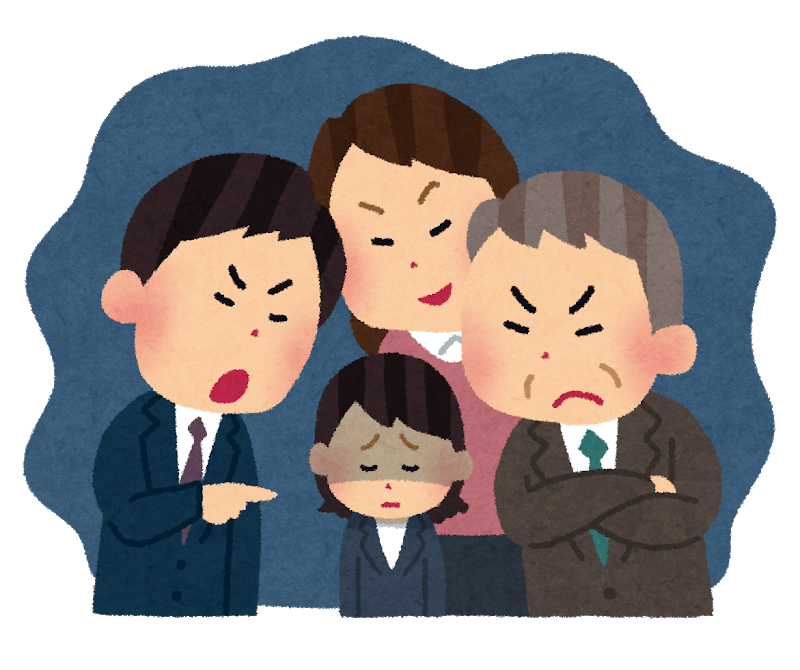
仕事の量は増える一方で、許容範囲を超えてしまうと燃え尽き
心身ともに疲れ果て、退職後ひきこもりになるという例もあるそうです。
まとめ
まるで自分のことを言われているかと思いました。
幼少期から親の暴力を受けて育ち、
言いたいことを言えずに、職場でもいじめに必死に耐え
そして退職後はひきこもりになる。
不幸の典型だとさえ思ってしまいました。
もちろん、自分よりも不幸な人はたくさんいると思いますし
世界で一番不幸だとは思いませんが
解決法や選択肢が少ない、
現在の日本の社会的な仕組みや構造の中では
一度レールを外れ、失敗した人が這いあがるのは難しい
一人前の生活に戻るのは極めて難しいと感じています。
私は仕事を辞めてから
親の介護もしながらひきこもっていたため
新しいタイプのひきこもりと思っていましたが、
本人の資質的にも問題があり、
もともとひきこもりになる要素があったのだと
この本を読んでそう思いました。
自分を信じられないことがつらい
生きる希望が見えない
このあたりのことは自己肯定感を上げて解消していくほかなさそうです。
自己肯定感については
また記事にあげていく予定ですので後日編集します。
最後までお読みいただきありがとうございました。

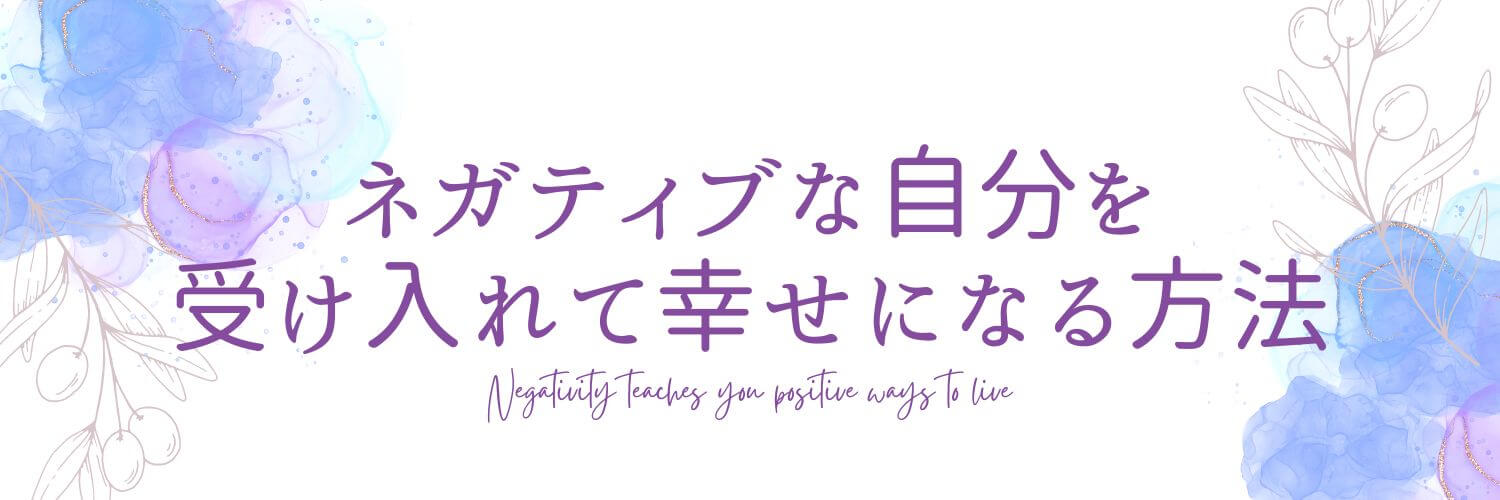


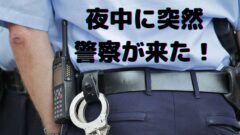




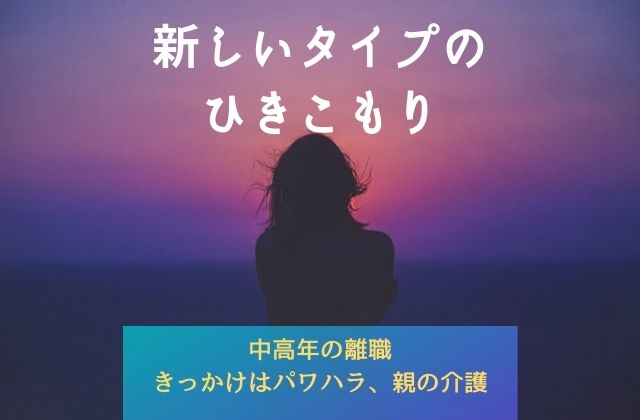
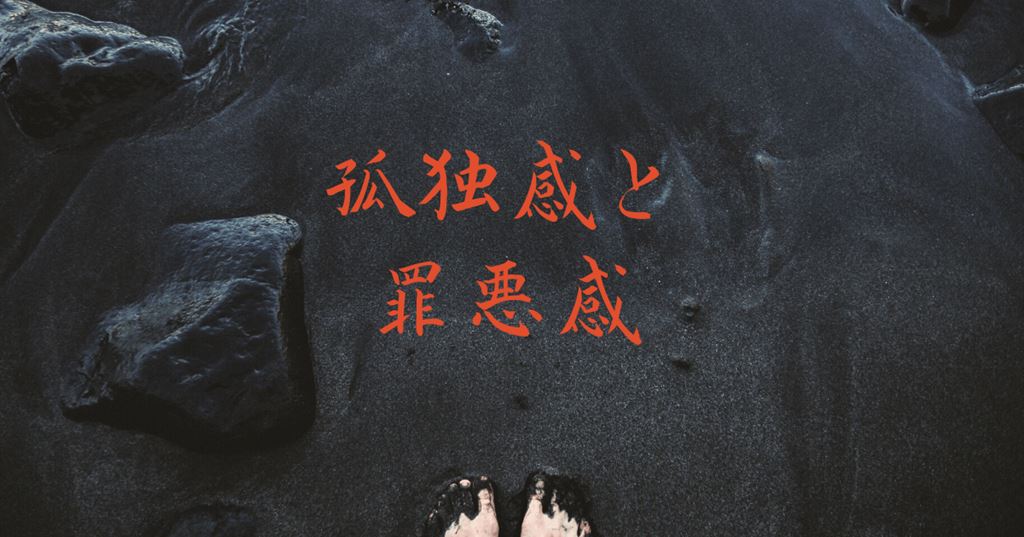
コメント